こんにちは、riricaです。
「二級建築士の受験を考えているけど、独学で合格できるのかな?」
「独学で勉強する場合、どんなテキストを使うのがいいのかな?」
と不安に思う方も多いと思います。
二級建築士の試験は年に1度しかなく、そのため多くの受験生は資格学校に通って勉強しているのが実情です。
しかし、実際私は令和2年度の二級建築士を学科・製図ともに独学で合格できました。
初受験でしたし、勉強は学科試験の3か月前の4月中旬から始めました。
短期間の勉強にも関わらず合格できたのは、正しい教材を効果的に使えたからだと思っています。
そこで今回はそんな私が実際に使用し、
本当にオススメする二級建築士(学科対策編)のテキストを3つ紹介したいと思います。
そして後半には、資格学校に通わなくても学科試験に合格できると思う理由を話していきます。
独学にお勧めのテキスト|3冊で大丈夫!
二級建築士のテキストは大きく3種類あります。
それが
・参考書(教科書みたいなもの)
・過去問題集
・分野別問題集
です。
私は
参考書 1冊
過去問題集 2冊
分野別問題集 なし
の計3冊を所有していました。
1つずつ詳しく説明していきます。
参考書(教科書みたいなもの)
まず参考書ですが
使用したものはこちら、「スタンダード」です。
 スタンダード 二級建築士 2021年版 [ 建築資格試験研究会 ]
スタンダード 二級建築士 2021年版 [ 建築資格試験研究会 ]
これは独学での受験をお考えなら購入したほうが良いと思います。
まれに、参考書は使わずに過去問を解きまくって合格!
みたいな勉強法をオススメしている方もいらっしゃいますが、
年々過去問以外からの出題が増えている建築士試験を一発合格したいのなら
参考書は1冊持っておき、
過去問に出題されている問題以外の知識を少しでも頭に入れておくのがベストです。
このスタンダードという参考書は
試験範囲を全て網羅できているとは言い難いですが、合格には全く問題ない量載っていますし
ページ数も多くなく、読みやすいと思います。
この参考書に載っている情報と他の過去問等を組み合わせて勉強すると
確実に合格できる実力はつけることが出来ます。
過去問題集
次に過去問題集です。
私は2冊所有していました。
というのも、
市販の過去問題集は1冊あたり7年分の問題しか載っておらず、
それより昔の問題も解きたかったので2冊購入したというだけです。
1冊が市販の総合資格学院の「過去問スーパー7」です。
参考までに画像を載せます。2022年度版は10月以降に販売されると思われます。
できれば最新版が良いです。
なぜなら法規の法改正に対応していることと、直近の過去問傾向を知ることが出来るからです。
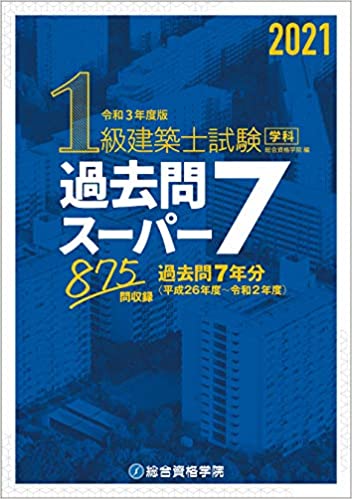
また、合格のためには7年分では心許ないので、それより前の過去問も入手した方がいいです。
2冊目の過去問については、同シリーズの2015年版を購入する方法もあります。
参考までにリンクを貼ります。
 【中古】 2級建築士試験 学科 過去問スーパー7 /総合資格学院(編者) 【中古】afb
【中古】 2級建築士試験 学科 過去問スーパー7 /総合資格学院(編者) 【中古】afb
もう一つの選択肢はフリマアプリで購入する方法です。
私はフリマアプリで購入しましたが、どんなものを購入したかと言うと
平成13~平成23年の過去問が載っている資格学校の問題集です。非売品です。
特に10年以上前の過去問を個別で入手するのはかなり難しいので
過去に受験された先輩がいれば過去問を頂くか、通販サイトやフリマアプリで買うのがいいと思います。
過去問題集はどれを選べばいいの?
過去問題集を選ぶ際、
「過去問題集ってたくさん出版されているけど、どれを選べばいいかわからない・・」
という方もいらっしゃると思います。
そんな方は、お持ちの法令集と同じ会社が出版している過去問題集を買うことをオススメします。
というのも、法規の解説において「法令集P.○○に記載」などというようにページが書かれており
それが他社の法令集だと少しページがずれてしまうためです。
そのため私は法令集と同じ総合資格学院の過去問題集(一つは市販のスーパー7、もう一つは非売品の11年分のテキスト)を使用して勉強しました。
ちなみにですが
総合資格の非売品テキストと市販の過去問題集でお悩みの方、どちらでも問題ありません。
過去問なので掲載されている問題は同じですし、解説も大差ないです。
違いとしては、
市販の過去問題集は年度ごとに問題が収録されておりますが、非売品のテキストは分野別に収録されています。
自分の勉強方法に沿ったものを選択するのが良いと思います。
法令集は日建学院のものを使っているという方には過去問題集はこちらの「チャレンジ7」が良いと思います。
 2級建築士 過去問題集チャレンジ7 令和3年度版 [ 日建学院教材研究会 ]
2級建築士 過去問題集チャレンジ7 令和3年度版 [ 日建学院教材研究会 ]
また、「過去問は何年分やればいいのか・・?」というお悩みもあるかと思いますが
私個人としては
過去問は最低10年分は解いた方が良いと思います。
資格学校ではおおよそ10~12年分の過去問に加え、新傾向問題も対策して試験に臨んでいます。
そのため、独学で試験に挑む際は、最低でも10年分の過去問を解けるようにした方が
良いと思います。
分野別問題集
そして私は購入しませんでしたが、
最後に分野別問題集です。
有名なものであれば、総合資格学院の「厳選問題集500」などがあります。
 2級建築士試験学科厳選問題集500+100(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]
2級建築士試験学科厳選問題集500+100(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]
過去問が分野ごとにまとめられており、ある分野を集中して勉強したいときには役立つと思います。
しかし、
出来るだけ予算を抑えて勉強したい方や、試験まで日程的に余裕がない方は
勉強初めに無理に揃える必要はないと思います。
勉強していくうちに苦手な分野がはっきりとし、必要であれば購入するのが良いでしょう。
先ほども言いました通り、私は結局買いませんでした。
というのも、苦手な分野の勉強にも過去問を使用したからです。
二級建築士試験において
同じ分野の問題は、毎年おおよそ同じような問題番号で出題されているので
過去問で苦手分野だけを効率よく探し出し、勉強することも可能なのです。
ではこれらのテキストを使用して効率的に勉強する方法について説明します。
各テキストの効果的な使い方
私の場合は4月から勉強を始め、7月の試験まで3ヶ月しか勉強期間がありませんでした。
そのため、効率よく、そして確実に合格できるように計画立てて勉強をしました。
独学者のためのテキストの効果的な使い方としてポイントは3つあります。
①計画を立てる【6月中旬までに過去問を2周解く】
②勉強の順番【法規】→【構造】→【計画・施工】
③9割過去問、1割参考書
以上3点です。
①計画を立てる
これは当然のようで、意外と忘れがちなのではないかと思います。
勉強を始める前に必ず計画を立てて下さい。
勉強を始めてから6月中旬頃までに過去問10年分を2周できるよう計画すれば問題ないでしょう。
6月後半は苦手な問題対策を行うため、
また、やはり計画はズレ込んだりしますので余裕を持って6月中旬に解き終わる計画にしましょう。
②勉強の順番は【法規】→【構造】→【計画・施工】
勉強順は【法規】から始めることをオススメします。
というのも、
法令集を引いたことが無い方にとって、法令集を引くのはとても時間がかかります。
私は、10年分の過去問を1周するだけでも2週間ほどかかりました。
同様に
【構造】の計算問題においても、解けるようになるまで時間がかかる場合もあるので
早めに取り組むことをオススメします。
問題としては5パターンほどしかありませんし、
構造の計算問題は全問確実に得点すべき問題ですので、頑張りましょう。
そのほかの【計画】【施工】【構造(計算問題以外)】については順番は問いません。
苦手そうな分野から潰してゆくのも一つの手かと思います。
③9割過去問、1割参考書
はい、これは具体的な勉強の進め方ですが、
2級建築士の試験では新出の問題が増えているとはいえ
ほとんどが過去問からの出題となっています。
そのため、過去問を中心に、そして
各問題の1周目は参考書で知識の補充をしつつ進めていくのが良いと思います。
2周目では正解した問題と間違えた問題を分かりやすいマークを付けつつ進めます。
3周目は間違えた問題のみ解き、参考書の該当ページも再度チェックします。
このように過去問全問を2周+間違えた問題1周を行い
勉強時間として9割を過去問を解く時間に、残り1割を参考書を読んで知識を補充する
という時間配分で勉強を行うと効率良いと思います。
私も6月終わり頃までに過去問を2周〜3周して、全体の8割方の問題には正解できるようになっていました。
試験本番まで10日を残してこの段階で、過去問を8割解くことが出来れば
合格ラインまできていると思います。
残り1週間では、苦手分野を過去問から探して何度か解くと良いでしょう。
しかし、ここまで読んで
「やはり一人で勉強時間を確保できるのだろうか・・」
「資格学校に通うほうが多くの問題数をこなせるのではないか?」
と感じた方もいるかもしれません。
そこで独学で可能な理由を話します。
資格学校に通わなくても大丈夫な理由
それは、ズバリ
資格学校に通っても、結局勉強するのは自分だから。
です。
資格学校では問題の解き方や解説についての講義を受けることはできますが、
結局、宿題が出て問題は自宅で解くことになります。
どうせ家で解くのなら、独学でもできる。と考えています。
もちろん出題されやすい問題傾向や、新傾向問題などは資格学校のほうが効率よく学べます。
しかし何度も言っていますが、試験で出題されるのはほとんどが過去問からです。
なので、まずは過去問を解いてみましょう。
二級建築士の学科試験の問題はほとんどが暗記科目ですので
きっと独学でも勉強できるのではないか?ということに気づくと思います。
まずは少しでも早いうちから
法令集と過去問、そして1冊の参考書を購入して
二級建築士の試験勉強を始めましょう!
法令集のオススメはまた別の記事で書こうと思いますが、私が使っていたのはコチラの総合資格学院のものです。
 建築関係法令集法令編(令和3年版) [ 総合資格学院 ]
建築関係法令集法令編(令和3年版) [ 総合資格学院 ]



コメント